
セルフビルドやDIYで、家を建てる前に必要な、手続きについての記事です。
建築確認申請や、4号特例の見直し、建築確認申請を省略可能な場合についても触れておきます。
家を建てる前に必要な手続き
家を建てる前に必要な手続き、主に建築確認申請に関係する事柄についての記載です。
(土地、住宅ローンなどに関する手続きは割愛します。)
建築確認申請は、自治体の建築指導課、もしくは民間の審査機関に、
諸々の書類を用意して、確認申請を行います。
問題がなければ、確認済証が交付され、実際の工事に入る、
といった、ながれになります。
ここまでが、事前の手続きです。
以後、工事が終わったら、完了検査申請を行い、
最後に検査員が実際に現地に赴いて完了検査を行います。
問題なければ、検査済証が交付されます。この後、引き渡しになります。
(規模が大きい場合、途中に中間検査が行われる場合も、あります)
建築確認申請に必要な書類
建築確認申請に必要なものです。
- 確認申請書・・・書式は、自治体のホームページや、建築指導課で入手できます。指定された書式に必要事項を記入して提出します。
- 設計図・・・配置図、求積図、平面図、立面図、断面図などの必要図面。
- 構造計算書・・・構造計算書の添付が必要。
- 省エネ関連の書類・・・省エネ関連の書類の添付が必要。
- 建築設備に関する書類・・・消防設備、給排水設備など、設備関係の書類の添付が必要。
- 敷地に関する書類・・・敷地の求積図、公図、測量図など、敷地の位置関係が分かる図面。
- その他の書類・・・自治体によって、別途、必要とされる書類がある場合があります。事前に、建築指導課などに確認しておいた方がよいと思います。
申請には、様々な図面、書類、を用意しなければなりません。
この為、設計士等に依頼するのが、一般的です。
2025年、4号特例が無くなりました
いままで、一般的な木造住宅の多くは、
4号建築物として構造計算書の添付が免除されていました。
これは、4号特例と呼ばれていましたが、
新たに建物の省エネ基準への適合が義務付けられることに伴い、
2025年、法改正により、4号建築物は廃止されて、新2号建築物と新3号建築物に分けられることになりました。
木造2階建て、もしくは、延べ床面積200㎡を超える木造平屋建て
全ての地域で、建築確認、検査が必要。
延べ床面積200㎡以下の木造平屋建て
都市計画区域等内は建築確認、検査が必要。
都市計画区域等以外の地域では建築確認、検査が省略可能。
新2号建築物と新3号建築物の分かれ目は、
- 平屋建てか、2階建て以上なのか、
- 延べ床面積200㎡以下か、それ以上なのか、
ということで、建物の大きさ(規模)によります。
また、都市計画区域等以外の平屋建てのみ、建築確認申請の審査省略制度の対象となります。
これによって、2階建てなど多くの建物が、構造計算や省エネ対策を行うことになり、
より安全性や省エネの担保された家を手に入れることが、できるようになりました。
一方で、これが、住宅価格に影響するのは、確実だと思います。
4号特例が変わります・・・国土交通省のページです。pdfが開きます。
セルフビルドで素人が、建物を設計できるのか?
素人が、建物を設計できるのか?
大豪邸もつくれるのか?
気になります。
答えは、最初の問いは、条件付きで〇、
次の問いは✕、になります。
というのも、建物を設計する際には、
設計できる大きさ(規模)に制限があります。
これは、プロである建築士であっても、です。
建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士、と分かれていますが、
大きな違いは、設計できる建物の大きさ(規模)です。
木造建築士は、小規模の木造建築物のみ、
二級建築士はそれ以外にも、鉄筋コンクリート造(rc造)などの設計もできますが、
規模にはいろいろと制限があります。
一方で、一級建築士には全ての建築物に対して制限がありません。
一級建築士は、学科、製図に加えて実務経験も加味される試験を受けて合格した、
設計業務のエキスパートです。
さて、プロですら厳しい制限が課されている設計業務、
素人が、建物を設計できるのか?
最初の問いに戻ります。
2階以下、かつ100㎡以下の木造建築物なら、設計できる。
というのが、正確な答えです。
セルフビルドやDIYを考えている方、大豪邸はNGです。
また、建築士でなくても設計は可能ですが、
これは、建築基準法を無視してよいということでは、ありません。
全ての建築物は、建築基準法を遵守する必要があります。
ゆめゆめ、お忘れなきように。
リンクを置いておきます。
建築士の種類と業務範囲・・・ページ内の表を見ていただくと、詳しいことが分かります。
セルフビルドの前に必要な手続き
セルフビルドの前に行う手続きは、上記したような建築確認申請になります。
建築確認申請は、本来、施主が行うものなので、
ご自身の家を建てる、ということであれば、申請すること自体は何ら問題ありません。
委任状など必要なく、むしろ本来のかたちになります。
設計も、木造で2階以下、かつ100㎡以下の建物なら、素人で行うことも認められています。
とはいえ、たくさんの図面や書類の提出が必要になる、ということは覚悟しておきましょう。
もし、申請が通らなかった場合でも、不備を訂正して、何度でも申請できます。
ただ、申請にも費用がかかるので、事前に十分検討してから、申請を行う必要があります。
また、条件によっては、建築確認申請の手続き自体を省くことができます。
例えば、私の場合、「都市計画区域外の新3号建築物」に該当するので、
建築確認申請は必要ありません。
事前に必要なのは工事届のみでした。
リンクを置いておきます。参考にされてください。
建築確認申請が不要になる7つの条件|4号特例廃止による改正点も解説・・・建築確認申請を省略できる条件が記されています。
DIYで,工事届を出してきました
上記のように、私の場合、建築確認申請は省略でき、事前に必要なのは工事届のみでした。
工事届とは、本来なら建築確認申請に付随して着工前に提出される書類です。
建築確認申請が、建築基準法に準じた建物の安全性を検査するのに対して、
工事届は、国が建物の建築状況を把握するためのものです。
なので、いつ、どこに、どのような建物の着工があったのか、といった事柄を示す手続きになります。
まず事前に自治体の窓口に相談してから、ひと通り必要事項を記入して、持っていきました。
そして、窓口でご指導いただきながら、添付書類(位置図など)と共に提出しました。
手数料を払えば、証明書も発行してもらえます。
届けを出すと、建築基準法以外の法令等に基づく手続きの主なもの、として別途用紙を渡されます。
そこに建築指導課、まちづくり推進課、建設政策課、耕地課、農業委員会、などの相談窓口と、建設リサイクル法等の相談すべき法令が、ずらりと並んでいます。
(自治体により違いがあるでしょうが、別途検討すべき法令があると思います)
私の場合は、その中で景観条例と、道路占有許可について相談する必要がありました。
これも、事前に確認して相談していたので、問題はありませんでした。
DIYやセルフビルドを考えている方は、事前にいろいろな所に相談に出向いたりすると思います。
このとき、自分のやりたいこと、やろうとしていることを真摯に話すことが大切だと思います。
私は、自身で設計、施工するつもりであることや、完成まで時間がかかることなどを説明しました。
建築指導課など対応いただいた方々は、こちらの意図を踏まえて親切丁寧に対応して頂きました。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
記事の題名に使っていて、何ですが、、
実は私、「セルフビルド」という言葉が、
あまり好きではありません。
逆に、「DIY」という言葉は、大好きなので、
当ブログでは、こちらを主に使ってます。
さておき、
「家を建てる」 というのは、
一般的な人にとって、生涯で一番、高価な買い物であり、
個人として提案する、最も大きな、プロジェクトになります。
資金を出すクライアントである、あなたの意向に、寄り添いながら、
たくさんの人たちが関わって、家をつくりあげていきます。
返して、自分で家を建てることを 「セルフビルド」 と呼びます。
私には、それがまるで、
自分一人で家をつくり上げていくかのような
傲慢な感じの響きに、聞こえてしまいます。
一人で、家は建てられません。
プラントで生コンを練って、ミキサー車で持ってきてもらわなければ、
生コン打設することはできません。
柱を刻むにしても、木を伐採して、運んで、製材して、乾燥して、持ってきてもらわなければ、
加工することはできません。
たぶん、一人でやろうとすればするほど、
そのようなことを痛感していく、と思っています。
この記事で、紹介している建築確認申請も、そうです。
専門的な知識や経験を持った建築士の方々から、アドバイスや協力があれば
より堅実で詳細な検討ができます。
セルフビルドを考えている方は、
そういったアドバイスや協力を得られる方々を
探してみることも視野にいれておくと、よいと思います。
仕事としての付き合いだけでなく、
良好な関係になっていけば、
それは「人脈」として、
大きな財産になっていくことでしょう。
私の場合は、相談できる建築士の友人がいて、
とても幸運だと思ってます。
いろいろ相談にのってくれて、
ありがとう。
(この記事にも目を通してもらいました)

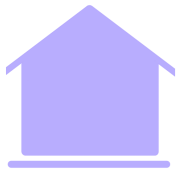
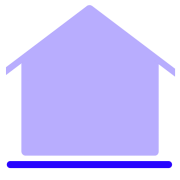

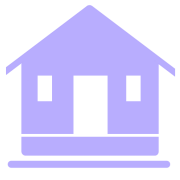
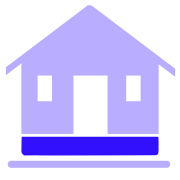
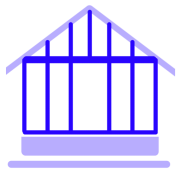
.jpg)

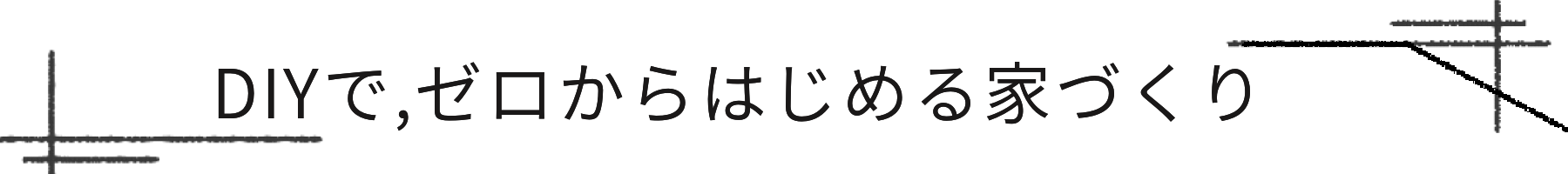
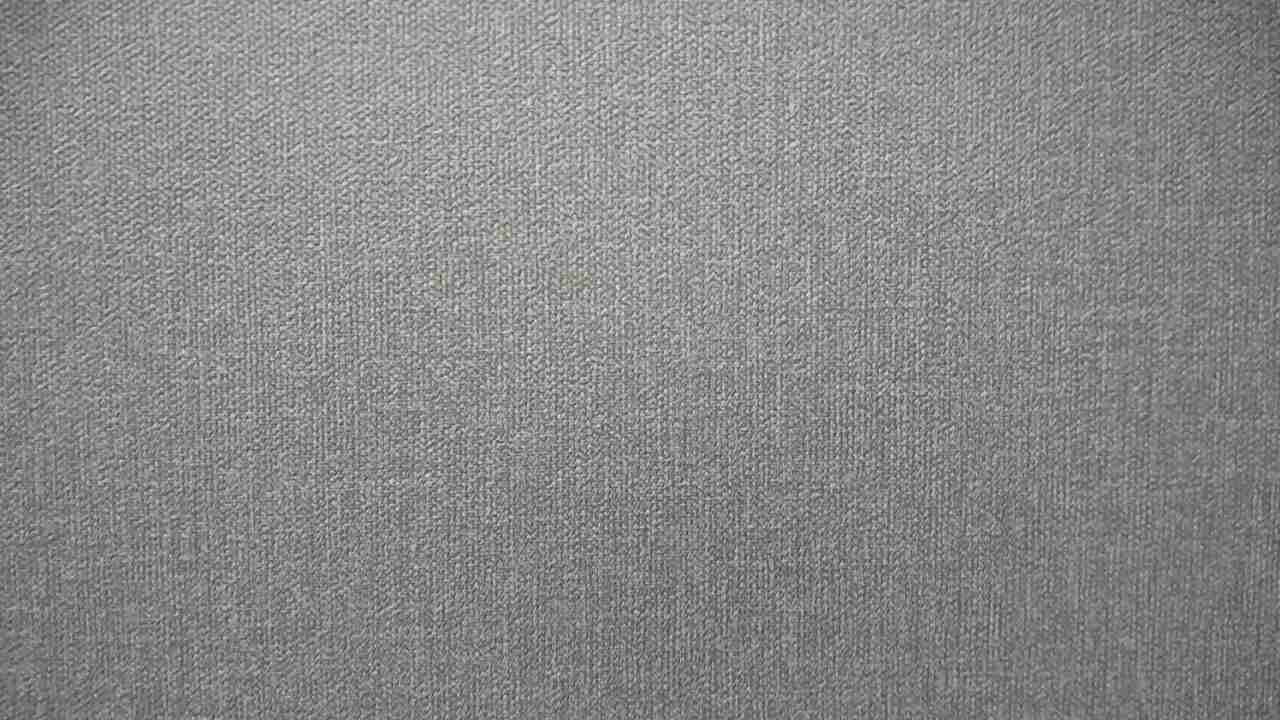






コメント
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)