前回の雑コンクリート工事の続きです。
在来工法浴室の土間コンクリート工事をしました。
セパレーターの後処理についても触れておきます。
在来工法の浴室床面の下はどうなっている?
新築住宅の浴室は、ユニットバスが主流となり、
在来工法の浴室は、少なくなってきている印象があります。
今回、私は在来工法で浴室をつくる為、資料を探したり、話を聞いたりしました。
浴室洗い場は、タイル張りになっているものが多く見られました。
で、このタイルの下の部分は、どうなっているのだろう?
いろいろとネットを探しても、どうも、ハッキリしません。
どうやら、土、とか、コンクリートで埋まっている、といった感じのようです。
リフォームで、たまたま在来工法の浴室をユニットバスに変えた方に話を聞いたら、
浴室床下部分は、土だったそうです。
他にも、古い浴室をDIYでリフォームした方に聞いても、
洗い場床下部分はコンクリートになっていた、とのことでした。
そこに、埋め殺し配管があったりする、とのこと。
というわけで、私も、洗い場床下部分は埋めてしまうことにしました。
ただ、埋め殺し配管にはしたくないので、マスを設置して配管を露出させるようにしました。
浴槽の下部分でも、コンクリートで覆って排水管を埋め殺して配管して、
浴槽本体とは、配管を繋がない、といった施工方法がよく見られるようです。
古い浴室をDIYでリフォームした方も、そのような構造になっていた、と教えてくれました。
この構造は、あとあと問題が出てきそうなので、
私は、配管を直接浴槽に繋いで排水しようと考えました。
浴室床面の雑コンクリート工事をしました
浴室床面の雑コンクリート工事をしました。
浴室立ち上がりに囲まれた場所(下写真)が、浴室洗い場になる部分です。

この部分に排水器具を付けて、
基礎立ち上がり天端と同じ高さの位置で土間コンを打設します。
ここまでが、今回の作業内容になります。
浴室洗い場床面工事は、この先まだ別の工程がありますが、
それはまた、いずれ別記事にします。(まだ、出来てません)
浴室床面の埋め戻し
このまま、砕石を敷き詰めてもよいのですが、
結構なスペースがあるので、そこらへんに散らばっている間知ブロックを敷きこむことにしました。

間知ブロックは、形がバラバラです。
高さに注意しながら、パズルのように並べていきます。

アレコレ入れ替えたりして、パズル完成です。
ここで、半分くらいまで砕石を入れておきます。
防水マスの設置
洗い場の排水ができるように、防水マスを設置します。
これは、後に設置する排水トラップとセットになっているものです。

上写真 右が防水マスです。
上写真 左は、型枠代わりに防水マスの下に置けるように塩ビ管を切って加工したものです。

防水マスの裏面です。
後でエルボを付けます。写真右は、使用したシーリング材です。

浴室立ち上がりの穴を通して、反対側に抜けるように排水経路をとっていきます。
まずは、仮組みしてみます。

排水は、水勾配をつけながら設置していくので、相応の高さが必要になってきます。
この勾配がきちんととれないと、水がスムーズに流れていきません。
この、高低差の確認は重要です。
今回は、高低差にあまり余裕がないので、慎重に確認します。

確認できたら、型枠を組んでいきます。
コンパネなどを切って用意します。(写真上)
今まで、紹介した型枠建て込みとは少し違うので、
ちょっと細かく紹介します。

塩ビ管にハの字にコンパネを差し込んで、角材(写真赤丸)を、
矢印の方向に軽く叩き込んで、かしめるようにして固定します。
塩ビ管の一部は繋がったままにして、
ここで、広がらないようにしてあります。
反対側から見ると、こんな感じです。(下 写真)
横に置いてあるコンパネを上に差し込んでいきます。

生コンを入れた後、枠はこちら側から、すべて取り除きます。
先ほど、打ち込んだ角材を、こちら側から押し出すように叩けば、
かしめた部分が緩んで、枠材が取れる、
というスンポウです。
釘、ビスなどを使うと、あとで枠をバラせません。
これは一例で、どのように、型枠を組んでも構いません。
ただ、バラすことまで考えておかないと、
後で、ギャフンとなります。

蓋をするように、コンパネを差し込みます。
後で抜きやすいように、キチキチに、ならないように高さを調整しておきます。

防水マスを置いてみて、位置確認します。
これは、後からこの上に設置する排水トラップの施工書に指定された寸法を確認しています。

外側にも型枠を付けて、生コンを入れていきます。

少量なので、手練りします。
手練りについては、以下の記事で触れています。ご参考に。

砕石を入れて、コンクリート練りします。
できたら、隅々まで棒などで突きながら、入れていきます。

固まったら、外枠を取っておきます。
ここで、残りの半分も埋め戻します。

縁起がいいので、ミラクルのかけら(バケツで固まった生コン 写真赤丸)も、入れておくことにしました。

埋め戻したところです。
砕石の部分は、基礎天端より100㎜下がったところに合わせます。

鉄筋も入れておきます。
一般的に構造部分に直接関係ない、このような土間コンには、
ワイヤーメッシュを使うことが、多いと思います。
ワイヤーメッシュとは、鉄棒を格子状に圧着してあるもので、バーベキューの網をでっかくしたようなものです。ホームセンターにも売ってます。

防水マスの周りに、セメントを手練りして詰めておきます。
隙間なく詰まるように、棒や手で押し込んだら、天端を均しておきます。

残りの部分は、生コン会社に頼んで、打ち込みすることにしました。
浴室床面の生コン打設
今回の打設メンバーは、ミキサー車(ドライバー)と一般作業員(私)の2人です。
前回の雑コン打設でもお願いした、小型のミキサー車(5t車)で、
基礎の奥の方まで車を寄せてもらいます。
そこから、直に土間コン打設です。

生コンを流してもらいながら、カキ板で広げていきます。

板で天端を均等に広げていきます。
今回の土間コンは、基礎の天端に合わせるだけなので、やりやすいです。
広げたら、コテで表面を均しておきます。
土間コン打設完了です。
余った生コンは、別の場所に、広げておきました。

後から、また天端をおさえていこうと思っていましたが、
雨、降ってきました。
慌てて、シートをかけます。

そのまま、しばらく降り続きました。
これにて終了です。
セパレーターの後処理
土間コンを、養生している間に、セパレーターの後処理をしました。
セパレーター(以後セパ)は、生コン打設の際、型枠の保持におおいに役立ってくれます。
ただ、型枠を外した後では、鉄棒部分が露出することになります。
この部分の錆びを防ぐため、モルタルで埋めるなど、何らかの後処理が必要です。

セパのハット部分が露出している様子です。(上写真)
ハンマーで、何度か叩いても取れるのですが、
セパ折り(下写真 銀色の棒)という、この部分を折り取るための便利な道具があります。
これを、突き出た鉄棒に差し込んで、上下左右にグリグリします。

何度かやると、ハット部分がポロっと取れます。(写真)

ハット部分を取った状態です。
ここを、モルタルで埋めていきます。
この部分が、ネジ式になっている「Pコン」というものもあります。
そちらのほうが、一般的かと思います。

モルタルを練ります。
モルタルとは、セメント、砂、水、を混ぜたもので、砕石など大きな骨材は入れません。
強度を必要としない補修や、壁塗りなど、いろいろな場面で使用されます。

モルタルを穴部分に、手でグリグリ詰めていきます。
ちなみに、ここをキレイに仕上げたものが、コンクリート打ち放しの壁面にある、
丸い模様みたいなものです。
(コンクリート打ち放しの壁面も、最近は打設後そのままの状態ではなく、全面仕上げ直して打ち放し風にしたものが多いです。)
今回は、見える部分ではないので、埋めるだけという感じです。(下写真 赤丸)

立ち上がりの付け根にノロが出ている部分があります。(上写真 四角)
こういった部分も、キレイにしておきます。(下写真)

最初は、バールやヘラなどで、取っていましたが、
後から、工具に付けるハツリ用のピックを使ったら、やりやすかったです。(下写真)

そうこうしているうちに、養生期間が終わり、シートを外してみました。

浴室の土間コンクリートです。(上写真)
雨の跡がたくさんついてます。
美しくないですね。
いずれは、この上に防水処理を施すので、見た目は気にしないことにします。

排水経路の型枠も外します。

中の様子です。(上写真)後ほど、奥に見える丸いところに、排水管をつなぎます。
これで、雑コンクリート工事は、概ね完了です。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回の、生コン打設日は天気予報で「くもり」になってました。
しかし、当日は微妙な天気でした。
若干の不安はありましたが、
打ち込み自体は問題なく終わり、
ホッとしたのも、束の間、
「天端おさえ」をしていたところ、
降りだしました。
チクショー、やっぱりか。
と、なりました。
一般的に、生コン打設日は「晴れ」の日を選びます。
ですが、それは生コン打設を控えている業者さんも同じです。
当然、生コン会社の予約も込み合います。
ちょっと、微妙な天気予報の日は、
空きがあったりします。
こんな感じです。
さて、長かったベタ基礎施工も、
これでだいたい終わりです。
これから、この上に建物が立ち上がっていきます。
【建て方編】で、お会いできたら、うれしいです。
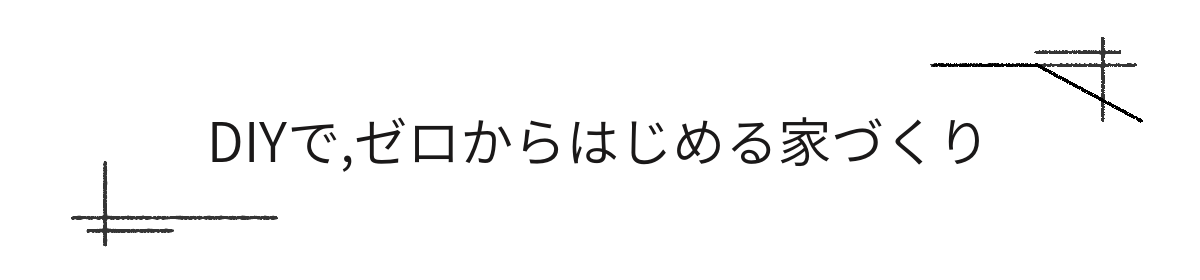
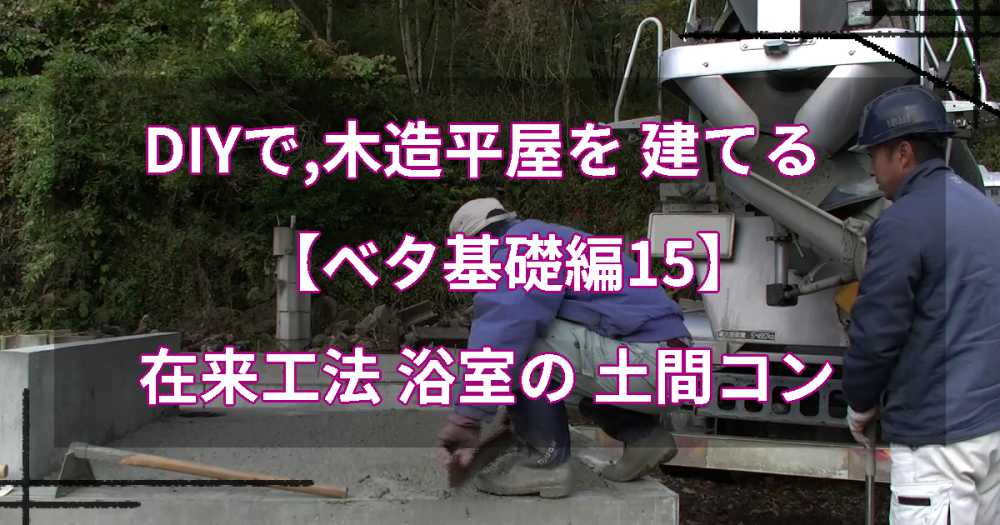

コメント