地盤調査の方法と準備、立ち合いについての紹介です。
地盤調査とは、
地面は、一見しただけは中まで分かりません。
地盤調査とは、建物が建つのに適した地盤かどうか、地面の中を調べるものです。
地震などによって液状化を起こして傾く、とか
盛土の部分が崩れ落ちる、など、痛ましい報道に覚えがあるのではないでしょうか。
このような事柄を防ぐためでもあります。
瑕疵担保保険に申し込む際にも必要な事柄なので、ハウスメーカーや、工務店も必ず行っています。
地盤に問題がある場合は、地盤改良を行う必要がでてきます。
地盤改良工事には、石灰を混ぜ込んだり、杭を打ち込んだり、など、いろいろと種類がありますが、いずれにしろ、追加で費用がかかります。
(土木の話ですが、石灰を重機で土に混ぜ込んで地盤改良する現場がありました。
粘土質のブヨブヨした感じの地面でしたが、改良後は結構短時間でガチガチになります。)
地盤調査の方法
地盤調査の方法は、以下の3つが一般的に多く行われていると思います。
・「スウェーデン式サウンディング(SWS)試験」・・・ロッドと呼ばれる大きな鉄の杭を地面に差し込んでいき、地面の中の状態を調べます。
・「ボーリング調査」・・・やぐらを組んで、実際に地面に穴を掘って中の状態を調べます。
・「表面波探査法」・・・実際に地面をいじることは無く、振動を起こす装置(起振機)とそれを受信する装置(検出器)を複数地面に置いて、振動の検出時間の差から地面の中を調べます。
表面波探査法以外は、実際に敷地で調査を行い、私が立ち合いましたので後述します。
専門家のリンクを置いておきます。
戸建住宅の地盤調査法・・地盤調査の方法や、液状化についても解説されてあります。
地盤調査の事前準備
いずれの方法で地盤調査するにせよ、敷地内の建物の位置は出しておきます。
スウェーデン式サウンディング(SWS)試験だと、5か所くらい計測するのが一般的です。
事前に、建物の四隅と、中心の位置が分かるように杭などを打って番号を振っておきます。
地縄張りのようなキッチリした点を示す必要はないので、ある程度の場所が分かればOKです。
スケールや巻き尺を使う矩(直角)の出し方を書いてあります。ご参考に。
私の場合は、当時計画していた建物は四角形ではなかったので、測量してピッシャの位置に杭を打ちました。
測点(測る場所)は5点にしました。
これは、地盤調査会社の標準料金が5点計測になっていたからです。
測点が一つ増えるごとに追加料金がかかる仕組みでした。
この会社は、見積もりを取った段階でしっかりとした料金体系を示して頂き、
とても分かりやすかったです。
対応も、とても丁寧でした。
今回のDIYは、業者の選定と依頼、調査日の打ち合わせ、測点の設置など、調査までの段取りです。
実際の調査は、業者の方にお願いしたので、私は立ち会っただけです。
スウェーデン式サウンディング(SWS)試験
スウェーデン式サウンディング(SWS)試験の測定機器です。

写真にあるような自走式のタイプは、機械が歩いて測定位置まで行き、ロッド(写真 赤線)と呼ばれる鉄杭を打ち込んで検査します。
ロッドが入り込んでいかなくなったら、荷重(重し)を加えて(写真 赤丸の部分)更に計測します。
このロッドにどれだけの負荷がかかるかで地面の中の様子を調査します。
このように、スウェーデン式サウンディング(SWS)試験は測点をロッドが入る点で計測するものです。
このため、測点の下に大きな石など障害物があると、それ以上計測することができません。
今回の場合でも、1点 途中で計測できなくなったところがありました。
そのような場合は、近くに測点をずらしてやり直します。
計測した場所は、枝番(1-1、1-2など)としておきます。

立ち会っている場合、
「こちら側にずらして、測り直すという事でいいですか。」
「問題ありません。よろしくお願いします。」
など、その場で確認できるので、よいです。
あと、職人さんとお話できます。
これが、楽しいです。
(もちろん、お仕事の邪魔にならないようにしますよ。)
作業は、半日くらいで終わります。
検査結果は、後日送られてきます。
結果は、木造住宅を建てるのに何ら問題ない。
というものでした。
実はこの場所は、今回の建築予定地ではありません。
プロフィールで触れていますが、同じ敷地で以前計画していた場所になります。
ボーリング調査
ボーリング調査は、やぐらを組んで地面に穴を掘っていくものです。
穴を掘りながら、掘った部分の土を取り出していきます。
実際に地面の中の土が見えるので、より確実で詳細なデータが得られます。
使用する機材も大きくなり作業に日数がかかるため、例示した他の地盤調査より高額になります。
それでも、当時計画していたものは鉄筋コンクリート(RC)造の建物だったので、より詳細なデータを得るためにボーリング調査も追加で行いました。
こちらも、同じ業者さんにお願いしました。

(写真 やぐらを組んでいく様子)
ユニックなどが入っていける場所でなければ、機材を入れるのが難しいと思います。

やぐらができたら、サンプルを取りながら掘り進めていきます。
掘り進めた筒をパカッと開いて、中の土が取れるようになっています。

10Mくらい掘る予定でしたが、途中の段階で問題ないという見解になりました。
実際は、7M掘りました。
掘削は、地質調査技士という資格を持った地質のプロが行うので、その方の意見と、構造建築士の意見を伺ってのことです。
掘削の費用は調査費+M単位だったので、予定していた金額より安く済みました。

調査が終わると、調査結果を詳細にまとめた冊子と、立派な箱に入った土のサンプルをもらいました。
中には、ボーリング調査で掘った土が、深さごとに分けられて入っていました。
自分のところの地質標本というのも、なんだか不思議な感じがします。

調査結果は、SWS調査に続き、問題なし(地盤改良などの必要はなし)ということでした。
今回の建築予定の場所は違いますが、同じ敷地内なので、この結果をもとに地盤に関しては大丈夫と判断しています。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
地盤調査をするにあたって、ネットなどで業者を探して、何軒も見積もりをお願いししました。
すると、見積額に百万円以上という、びっくりするような大きな差がありました。
この差額については、DIYで設計図を描いたら、やりたいこと の、おわりに一言で察してください。
(結果的には、誠意ある良心的な業者に依頼できました)
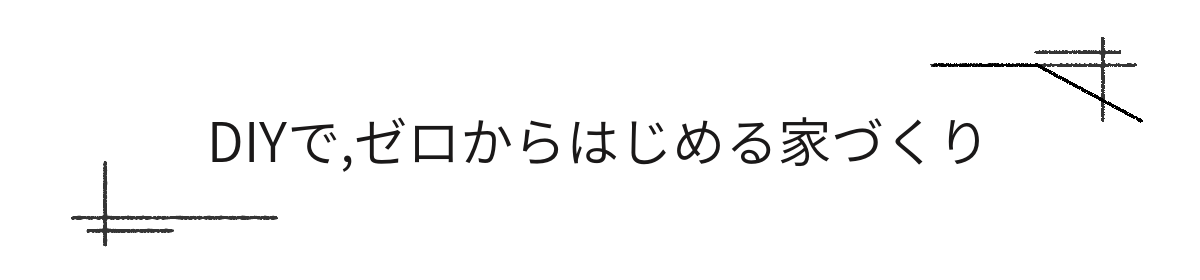




コメント