丁張り、砕石の敷き込み、捨てコンまで、終わったので基礎の外側部分の位置に型枠をつくる作業の紹介です。
あわせて、型枠をつくるのに必要なものや、矩の出し方、わかりにくい用語などについても触れておきます。
型枠とは、
型枠とは、文字通りコンクリートの型をとるための枠組みのことです。
一般的には、木枠(木製型枠)、金枠(鋼製型枠)が、多いと思います。
なかには、事前にユニット化されたシステム型枠や、FRP、プラスチック、アルミなどを使った新素材系の型枠など、いろいろと種類があるようです。
リンクを参照ください。
型枠・・・ウィキペディアの解説です
型枠工事とは・・・いろいろな型枠(メーカー)が紹介されてます。いろいろな枠材があるのだな、と思います。DIYには、すこし縁遠い感じです。
私の場合、コンパネに桟木をつけてつくる木枠(木製型枠)で、つくっていきます。
加工しやすく、自由度が高いのでDIY向きだと思います。
コンパネとは、
コンパネとは、合板の一種でコンクリートパネルの略です。
生コンを流し込んだあとの仕上がりと、離型しやすいよう片面が塗装されたものが、用いられます。

一般的には、サイズ1800mm×900mm、厚さ12mmのもので、
写真のように黄色に塗装されています。
JAS規格品など、品質の保証されたものを使ったほうがよいと思います。
合板にも、用途に合わせていろいろなサイズや種類があります。
詳しくは、専門家のサイトを参考にされてください。
ベニヤ・合板・コンパネの違いを理解しよう!それぞれの特徴を解説・・・合板の違いの解説
型枠サポートとは、
型枠サポートとは、コンクリート打設時の圧力に対して、型枠をしっかりと保持する役割を果たすものです。
一般的には、パイプを用いたパイプサポート式型枠支保工というやりかたが多いと思います。
私が知っているものは、バタ角と呼ばれる鋼管を、セパ(セパレーター)につけたホームタイという部材にクサビ止めして、枠をかためて(固定して)いく方法です。
リンクを参照してください。
型枠支保工・・・ウィキペディアのページです。
コンクリート型枠の組み方とは!型枠工事の手順や施工方法を解説・・・写真つきで解説されてあります。パイプサポートの使われる様子がよくわかります。
私の場合は、今回サポートを使わない枠固めの方法でやりました。
ベタ基礎外周部の型枠を組みました
型枠などを組み付けることを、「建て込み」と呼びます。
今回は、下地のレベル(水平)が出ていないので、通常の型枠の建込みとは、少し違った感じで進めました。
一般的な建込みは、立ち上がり部分作業時のような感じになると思います。
ベタ基礎の外側のラインに、基礎天端+10cm程度の高さで、ぐるっと型枠を建て込んだら完了です。
桟木、345(サシゴ)、フカシ、レーザー墨出し器、面木など寄り道をしながら、様子を紹介します。
詳しくは、専門家のサイトを参考にされてください。
基礎型枠の施工手順 現場管理のポイントとは?・・・型枠工事のながれが解説されてあります。
桟木とは、
建築工程のなかで、いろいろな場面で出てくる桟木。
この工程では、型枠の下に敷きこむ部材や、枠状に組む部材のことを指してます。
型枠大工さんも、そのように呼んでます。
私のいる地域では、30mm×60mmの角材を使うことが多いのですが、どうも大工さんや地域によって使うサイズが異なるようです。
要は、生コン打設時のコンクリートの側圧(圧力)に耐えるだけの枠組みができればOKだと思います。
渡すという意味合いがある【桟】の文字なのですが、様々な場面で桟木と呼ぶものが出てくるので、よくわからないところがあります。
専門家のサイトを参考にされてください。
桟木(サンギ)とは? 意味や使い方・・・デジタル大辞泉からです。
【大工用語】同じ木材でも呼び方いろいろ⁉厚いか薄いかってのもあるから”わけわかめ”!(^^)の巻・・・こちらは、屋根に使う部材としての桟木が紹介されてます。

まず、地墨をもとに基礎外周に桟木をつけていきました。
その上にコンパネを天端が水平に所定の位置にくるようにあわせて、組んでいく感じでした。

(写真 型枠のラインが一番最初の基準線にした部分です )
枠の上部は水平ですが、下部は現場地盤にあわせてデコボコしています。
これを原寸合わせで加工していくので、わりと面倒な作業になります。
大矩(おおがね・直角)の出し方、345(サシゴ)
ここで少し、矩(かね)、直角を確認する方法について触れておきます。
大矩(おおがね)・矩(かね)とは、
建築で使う場合、矩(かね)とは、直角を意味しています。
大矩(おおがね)は、家の角のような大きな直角、もしくは、
直角をみるための大きな定規のようなもので、現場でつくって利用するもの、
を指す言葉だと思います。
私は、レーザー墨出し器を使ったので、大矩定規は、つくりませんでした。
自分が住んでいる地域では、直角になっていないとき、
「 矩(カネンテ)がでてない 」
などと言いますが、たぶん方言だと思います。
345(サシゴ・サンシゴ)とは、
現場で、直角をだすときの方法について触れておきます。
今は、トランシットやレーザー墨出し器などの精密機器があるので、必要ない場合も多いと思います。
そのような、便利グッズがない時に、巻き尺などがあればできる方法なので、知っておいて損はないと思います。
方法としては、3:4:5の比で寸法をあわせていく感じになります。
例えば、直角方向に3M、4Mと測って、印をつけます。

印と印の間、斜辺の寸法が5Mになっていれば、
直角になっていることを確認できます。

ピタゴラスの定理です。
三角定規です。
もちろん、二等辺三角形のほうの三角定規でも、確認することは可能です。
その場合、辺の比が1:1:√2に、なります。
計算機が必要ですね。
正方形に近い家だと、こちらのほうが向いているかもしれません。
できるだけ、長い距離で測るほうが、より正確に直角を確認できると思います。
ただ、テープ(巻き尺)で長い距離を測るとたわみます。
無理に引っ張ると伸びます。
力加減で、わりと数値が変わるので、お気を付けください。
専門家のサイトをリンクしておきます。
現場で簡単に直角を出す方法「さんしご」・・・「さんしご」とか、「さしご」などと大工さんによって呼び方が違うようです。
家のかたちは、四角形を基本にしたものが多いので、矩をみる場面はよく出てくると思います。
余談ですが、
なぜ、四角形が多いのか。
私見ですが多分、つくりやすい、からだろうと思います。
これは、コストを抑えることにも繋がります。
コンクリートのフカシ部分とは、
ちょっと型枠から話がずれるかもしれませんが、コンクリートのフカシついても触れておきます。
フカシとは、
コンクリートの「フカシ」とは、「増し打ち」とも呼ばれます。
おさまりをよくする為に、設けられているけれど、構造上は必要のない部分に、余分にコンクリートを流し込むこと、と理解しています。
意匠的にとか、施工しやすいようになど、理由は様々だと思います。
専門家のサイトを参考にされてください。
増し打ち部分の鉄筋について・・・専門家による丁寧な解説です。
フカシ部分を設定しました
私の場合は、現在の敷地地盤面(現状GL)にあわせてベタ基礎を敷設します。
現在の地盤面は水勾配がついているので、水平に設置する基礎と隙間ができる部分があります。
この部分をフカシとして、ベタ基礎をつくることになります。

(写真の板で示してある部分が、図面の基礎断面になります。
それよりも最大10cmの深さでフカシ部分があります。)
レーザー墨出し器の使い方、
ここで少し、レーザー墨出し器についても触れておきます。
レーザー墨出し器とは、
文字通り、レーザー光によって、墨出しを行う機械です。
機器を置いた場所から、正確に水平、垂直の光のラインを出力してくれます。
レーザー光は、機器を設置したポイントがわかる 「地墨点」 と、
縦方向の垂直を見る 「垂直(たち)ライン」 と、
横方向の水平を見る 「水平(ろく)ライン」がでるものが基本です。
ラインが、1、2方向だけに出るものや、
垂直(たち)が4方向、水平(ろく)が360度すべてに出る 「フルラインタイプ」 と、呼ばれるものもあります。
ラインの数は、多く出たほうが便利ですが、値段も高価になると思います。
内部構造は、振り子のようになっている 「ジンバル式」 と、
モーターで制御する 「電子整準式」 が主流です。
「電子整準式」のほうが、振動に強く、機器自体も高価なものが多いです。
レーザー光の色も、従来の赤色だけでなく、より見やすい、とされる緑色のものもあります。
これも、緑色のほうが高価になっています。
ただ、レーザー墨出し器がはじめて発売された頃と比べると、値段も随分と下がっていて、DIYで使用されている方も、多いのではないかと思います。
また、レーザー光が所定の位置にくると、音声や点滅などで知らせてくれる受光器があると、便利です。
レーザー墨出し器の使い方
レーザー墨出し器自体は、設置した場所から正確にラインを照らし出してくれる機器です。
そこで使い方ですが、基準となる線の始点(もしくは終点)に設置する(地墨点をあわせます)と、そこからの大矩を確認できます。
大矩に沿って所定の距離を測って、そこにまた機器を設置して大矩をだす、、、
このような感じで地縄張りのときも使いました。
単純に、水平、垂直の基準線を設けたいときにも便利です。
また、「水平(ろく)ライン」と受光器を使うと、回転レベルのように高さを測っていくことも可能です。
この場合、設置するのは全体にレーザー光が届く場所なら、どこでも構わないと思います。
当然ですが遮蔽物がある場合、その先にレーザー光は届きません。

(写真 黄昏時のひとときだけは、屋外でもラインを見ることができますね。)
レーザー光が示した場所に地墨を打っていきました。
通常、最初に地墨はすべて打ち終わっているところですが、この場所は何度も測り直しました。

(写真 上下の桟木を組みながら、ちょっと変わった感じで建て込んでいる様子)
ぐるりとベタ基礎の外周部分を囲めたら、完成です。

面木とは
角部分をなめらかにすることを「面取り」と呼びます。
面木とは、型枠に取り付けて、コンクリートを「面取り」した様にする部材のことです。
文字通り、木でできたものもあるようですが、一般的にはプラスチック製のものが多いと思います。
面木を取り付けました
型枠ができたら、この段階で、面木を取り付けておきます。
コーナー部分の2か所に付けました。

(写真 角の薄桃色の部分が面木です。セパ用の穴も事前に開けています )
45度になっている部分は、コンパネを角度切りすることで面取りしたようにしました。

(写真 型枠が45度に曲がっている部分と、
左側がベタ基礎にかかるコンクリート土間部分 )
あとから天端レベリングするため、基礎天端に面木は付けません。
そのまま仕上げ面になる場合は付けたりします。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
型枠をつくるにあたって、知り合いの型枠大工さんに話を聞きました。
サポートを使わずにできる組み方を教えて頂いて、勉強になりました。
サポート関係は、あとあと使う予定がないので、リースしないといけないかな、と考えていたので助かりました。
この型枠大工さんは、近所に住んでいる気さくな方で、付き合いも長く、一緒に仕事したこともあります。
このような方に出会えて、私は幸運です。

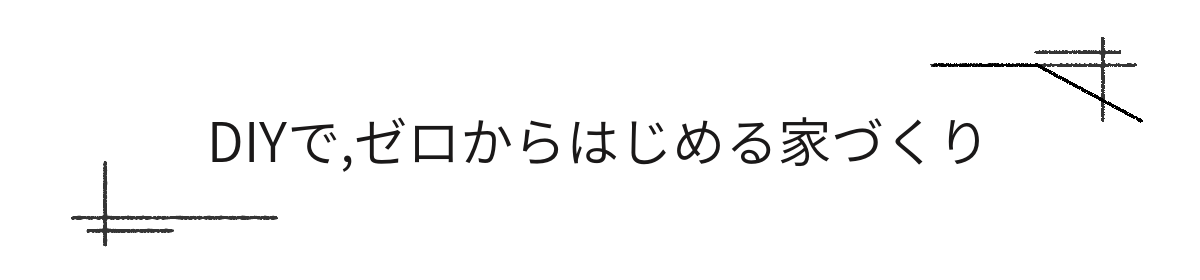

コメント