鉄筋を組み上げる作業を配筋と呼びます。
配筋の準備ができたので、型枠の中に鉄筋を組んでいく配筋作業の紹介です。
気になる鉄筋の錆についても触れておきます。
差し筋アンカーを、打ち込みました
一般的にベタ基礎では、配筋前に差し筋アンカーを打ち込んだりしません。
鉄筋のかぶりを考慮して全体が60mm以上地盤面から浮いた感じで組まれていきます。
そもそも、捨てコンは無筋で厚みもないため、差し筋アンカーは効かないと思います。
私の場合は、両脇の部分にコンクリート土間部分があるので、
そこに、差し筋アンカーを打ち込んで配筋の足掛かりにしました。

(写真 土間コン部分に差し筋アンカーを取り付けている様子)
アンカーは、コンクリートに下穴を空けて打ち込むタイプの、金属系アンカーです。
これは、配筋の補助を目的として設置したので、引張耐力を期待したものではありません。
とはいえ、何もしないよりは地盤面にしっかり固定されると思います。

(写真 差し筋アンカーは、東側西側の両方に600mmピッチで打ち込んであります)
この差し筋アンカーを取り掛かりにして、あばら筋を組んでいきます。

(写真 差し筋アンカーを足掛かりにしている様子)
セパレーターを、設置しました
セパレーターも先に取り付けて、あばら筋を組む足掛かりにしました。
まず、長めのセパレーターを、真ん中で切っておきます。

(写真 600mmのセパを鉄筋切りで半分にしているところ)
半分にしたセパを、スラブ配筋と同じ高さで、600mmピッチで設置していきます。

(写真 差し筋アンカーとセパを足掛かりにして配筋しているところ)
通常、セパは両側を止めますが、これは片側を鉄筋に溶接します。
そのため、片側のハット(取付ネジ等)は必要ありません。
「これならサポートを使わなくても、枠が張らずに(膨らまずに)打設できる」
と型枠大工さんから、教えて頂いた方法です。
外周部分を、配筋しました
あばら筋と横筋を200mmピッチの格子状にして組んでいきます。
横筋は上下がD13、中がD10です。
重ね継ぎ手が同じ場所にこないようにD13とD10は、ずらして配筋してあります。
これで、角に重ね継ぎ手が集中せずに配筋できます。

(写真 横筋D13で隅をずらして配筋しているところ 枠の上に準備しているのがD10)

重ね継ぎ手が、コーナー部分に集中していません。

(写真 外周部分のあばら筋を配筋したところ)
主筋を、配筋しました
外周部分のあばら筋ができたら、主筋を配筋していきました。
一般的に、主筋は短辺方向で下側(地盤側)に組んでいきます。
D16を使う立ち上がりのところが、鉄筋が込み合うと思い、
D16を、挟み込むように主筋の起点にしました。
隙間なく生コンを充填するため、鉄筋のあき(隙間)を気にしています。

(写真 立ち上がりの位置を確認して起点を決めている様子)

配筋する際は、高さ60㎜の角材に、150mmピッチの目盛りを書いて敷きこんでいます。
この角材は、段取り筋(配筋しやすいように反対側に先につける鉄筋)のような役割をしてます。
配筋するにつれて抜けなくなるので、だんだん短くしました。
配力筋を、配筋しました
通常、配力筋は長辺方向で上側(表側)に組んでいきます。
主筋がある程度並んだら、あわせて配力筋も組んでいきます。

重ね継ぎ手がずらしていけるように、矩(直角)になっていない方から組んでいきました。
主筋は2本でちょうどの長さだったので、中心で重ねていますが、
スラブ部分の配筋も重ね継ぎ手の位置は、できればチドリ(互い違い)に配筋したほうがよいと思います。
150mmピッチですべて配筋できたら、スラブ部分の配筋完了です。

サイコロ、ポリドーナツで鉄筋のかぶりを確保しておきます。

(写真 スラブ部分の配筋 立ち上がり部分のD16も配筋してあります)
セパレーターを、溶接しました
スラブ部分の配筋が終わった段階で、セパと鉄筋の接する部分を、点付け(ポイントのみ溶接)しました。

(写真 100V用の溶接機で作業する様子)

(写真 セパと鉄筋の交差する部分を点付け溶接 赤丸の部分)
今回は、型枠の補強を目的として一部のみ溶接するものです。
一般的には、配筋の際、鉄筋を溶接することは禁止されているそうです。
立ち上がり部分を、配筋しました
外周とスラブ部分ができたら、立ち上がり部分を配筋していきました。
土台芯のところに水糸を張り、位置確認しながら組んでいきました。

(写真 箱の上に置いてあるポールは、水糸の位置をおろすのに使ってます。)
この時、土台芯(壁芯)にあたる部分に縦筋をもってくると、あとのアンカー設置がやりやすいです。
私は、横筋が壁芯の位置にきて、アンカーを垂直に固定できないところがありました。

(写真 配筋の曲がりは、その場で随時曲げていきました。)
この部分の配筋も重ね継ぎ手の位置は、チドリ(互い違い)に配筋できるように、
あと、鉄筋が重なり過ぎないように配慮しました。

(写真 水糸を張って、確認しながら作業している様子)
補強筋を、配筋しました
次にスリーブ管の周りや、人通口の部分に、補強筋を配筋していきました。

(写真 赤色の線がスリーブ管の周りの補強筋です。)
スリーブ管の周りは、かぶりが足りなかったので、やり直してます。
用意していたパイプを入れて、かぶりを再度確認しました。

(写真 赤色の線が人通口部分の補強筋です。)
補強筋まで入れたら配筋完了です。

鉄筋の錆ついて
鉄筋、結束線など使用したものは新品で購入しています。
けれども、写真でお分かりのように、鉄筋や結束線はあちこちサビてます。
この鉄筋のサビ、結構、気になる方が多いみたいです。
私は、それほど気にしてません。
作業に時間がかかっているので、当然といえばそうなのですが、
実は、鉄筋は結構すぐにサビます。
表面の酸化被膜が崩れた曲げ部分や切断面からサビていきます。
雨で濡れたりすると、数日でサビてたりします。
結束線もそうです。
メッキ加工してあっても、割とすぐにサビます。
見た目は大丈夫かなという感じなのですが、
表面だけなので、それほど気にする必要はないと思います。
強アルカリ性のコンクリートに覆われてしまうと、
錆の進行は止まると思います。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
配筋の基本的な作業は、ザックリいうと、鉄筋を、切って、曲げて、並べて、結ぶ、です。
これで、ただの鉄の棒が建物のかたちに沿った複雑な骨組みになっていきます。
なんだか不思議な感じがします。
きれいに並んだ鉄筋は、コンクリートに埋まってしまうのが、もったいないような造形美があります。
プロの鉄筋工の方々は、これを、いとも簡単にサクサクと組み上げていきます。
もちろん、プロのようにはいきませんでしたが、生コンを打設するときは、
名残惜しい感じになりました。
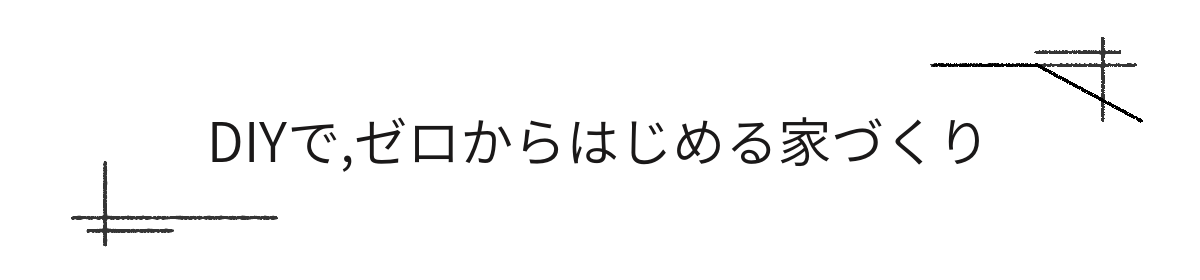

コメント