壁量算定図とは、壁面をもとに計算した数値で、建物の安全性やバランスを示す図面です。
DIYで描いた壁量算定図と、耐力壁、充足率判定や4分割法についてもあわせて紹介します。
※素人の私がDIYで、描いた図面の紹介です。
壁量算定図とは、
壁量算定図とは、壁量計算という手法で、建物が地震や強風にどれくらい対抗できるのか、バランスはとれているのか、といった事柄をみるものです。
開口部の無い壁(穴の開いていない壁)を「耐力壁」として、水平方向の地震の揺れなどに対抗する力として見なしていきます。
この「耐力壁」の量とバランスを計算してみたものが、壁量算定図になります。
注意したいのが、構造計算とは別のものである、ということです。
両者は似ていますが、構造計算のほうが建物自体の荷重など、考慮する項目が多いので、壁量計算より、しっかりとした根拠のある数値が出てきます。
計算方法も複雑で、一般的には、構造設計一級建築士など、構造計算の専門家に依頼します。
私は専門家ではないので、プロの方々のサイトや意見を参考にしてください。
リンクを貼っておきます。
耐力壁・・ウィキペディアによる耐力壁の解説です。
壁量計算 (壁量計算のフロー)・・モデルに従って、壁量算定していくことができます。
壁量計算と構造計算の違いは?1分でわかる意味、違い、木造、4分割法との関係
壁量計算(耐力壁図・判定) (例)・・国土交通省による例示です。(PDFが開きます)
耐力壁とは、
耐力壁とは、建物の中で水平方向の揺れや力に対抗することができる、とされる壁面のことです。
国によって認められた方法で施工されたものを、耐力壁とします。
軸組工法(在来工法)で例を挙げると、
開口部の無い、柱に挟まれた壁面であること。
かつ、筋交いのあるもの(筋交い耐力壁)、
または、構造用合板で覆われたもの(面材耐力壁)、
になります。
私の場合で、例を挙げると

写真の赤線で囲まれた部分が面材耐力壁になります。
窓を付けるために穴が開いている部分(写真 中央部)などは、耐力壁とはみなしません。
当然ですが、床面積や階数が増えると、必要になる耐力壁の量も増えます。
ところで、耐力壁には、施工方法によって、壁倍率というものを設けることができます。
壁倍率とは、
壁倍率とは、指定された方法で施工した場合に設けられる倍率で、
倍率によって実際の壁の長さより長い壁面として考えることができる、
というものです。
例えば、1Mの耐力壁があるとします。
ここに、たすき掛けの筋交いを入れると、
1MX4(倍率)=4Mの長さの耐力壁があると考えてもよい。
という感じで、実際の耐力壁より長く勘定できます。
これを存在壁量と呼びます。
壁量計算において、耐力壁の長さは=耐震性に関わってきますから、
バランスよく倍率の大きい耐力壁を配置することで、建物の耐震性を上げていくことができます。
以下、壁倍率の例です。
筋交いを入れる場合
- 片筋交い 30X90角材使用・・・1.5倍
- 片筋交い 45X90角材使用・・・2.0倍
- たすき掛け 45X90角材使用・・・4.0倍
面材(構造用合板厚さ7.5mm以上)を使う場合
- 面材張り大壁 N50釘@150mm以下・・・2.5倍
- 面材張り大壁 CN50釘@100mm以下・・・3.1倍
などです。
実際は、施工方法や、面材の厚さ、使用する釘、ピッチ(釘を打つ間隔)などによって
もっとたくさんの倍率が、細かく規定されています。
リンクを置いておきます。
合板耐力壁マニュアル・・・本当に、細かく決められています。(PDFが開きます)
構造用合板耐力壁の告示が変わりました・・施工方法による例示です。(PDFが開きます)
直下率とは、
耐力壁の話がでたので、直下率にも触れておきます。
直下率とは、構造に関する部分が階下と連続しているか割合で表すものです。
具体的には、
- 1階と2階で柱の位置が一致する割合・・・柱の直下率
- 1階と2階で耐力壁の位置が一致する割合・・・壁の直下率
柱、耐力壁、ともに50%以上が目安とされているそうです。
明確な基準はないようです。
2階建て以上をお考えの方は、検討ください。
お察しのとおり、当ブログのような平屋では関係ありません。
ご参考まで。
壁量算定図を描いてみました
私が描いたのは、充足率判定に関する図面と、4分割法に関する図面です。
プレカットの業者さんに、参考にしていただきました。
充足率判定とは、
充足率判定とは、建物の中に、地震や強風に対して十分に対応できるだけの耐力壁があるかどうかを判定するものになります。
どちらもX軸、Y軸それぞれに対して、計算します。
地震や強風に対して、それぞれ係数があって、建物の面積と掛け合わせて指標を算出します。
ここで算出された数値が、必要壁量になります。
これだけの壁がいりますよ、ということですね。
計算した存在壁量(耐力壁)が、必要壁量を上回ればOKです。
以下、私の場合です。
-800x565.jpg)
風に対する見付け面積用の図と、存在壁量用の伏図、あとは計算式になります。
4分割法とは、
4分割法とは、建物を4分割してそれぞれの存在壁量のバランスを考えるものです。
具体的には、
まず、X軸、Y軸それぞれの方向で建物を4分割します。(4等分に分けます)
その両端部分の存在壁量が必要壁量よりも上回っていればOKです。
それぞれの部分で、計算していきます。
-800x565.jpg)
4分割法に関する図面です。
いずれも、判定がOKになるようにします。
存在壁量の計算に際して、水色の部分は、45度の斜めの壁面になるので、
X軸、Y軸双方に半分づつ加える感じです。
私は、窓(開口部)を増やしたりしたので、何度かやり直してます。
建物が細長い形で、風圧に抵抗する短い部分の壁面が充足率を満たさなかったため、
その部分の壁倍率を、変更しました。
私は、面材(構造用合板)による方法で施工します。
尚、建物の形が不整形の場合は、4分割法ではなく「偏心率」で検証する場合があります。
偏心率とは、建物の重心と剛心(強さの中心)のずれをできるだけ0に近づける、
といったことのようです。(やっていないので、よくわかりません)
リンクを置いておきます。
木造 初めての壁量計算④(偏心率編)・・・偏心率の計算に関することが丁寧に解説されてます。
おわりに一言
最後まで読んでいただきありがとうございます。
壁量計算の計算式自体は、掛け算、割り算など小学校までに習うようなもので、それほど(斜辺部分を除く)難しいものではありません。
斜辺部分は、少し難しいかもしれませんが、算数が苦手の私でもなんとかできました。
繰り上げなど必要になる場合もあるので、単位に注意してください。
実際に計算する際に、参考にしたプロの方々のサイトのリンクを張ってあります。
あと、お察しの通り、壁量計算は外壁のみで行っています。
実は、石膏ボードを貼ってある内壁面でも、
耐力壁として適用される場合(開口部に注意)があります。
厚さ12.5mmを片面に貼っている場合は1倍、などです。
もちろん、筋交いなど入れれば、しっかりとした耐力壁になります。
私は、平屋で単純な形のため、外壁のみ計算して、内壁の分は+αとして考えてます。
セルフビルドを考えている方は、壁量計算を避けては通れません。
安全性に関する事柄です。しっかりと検討してください。
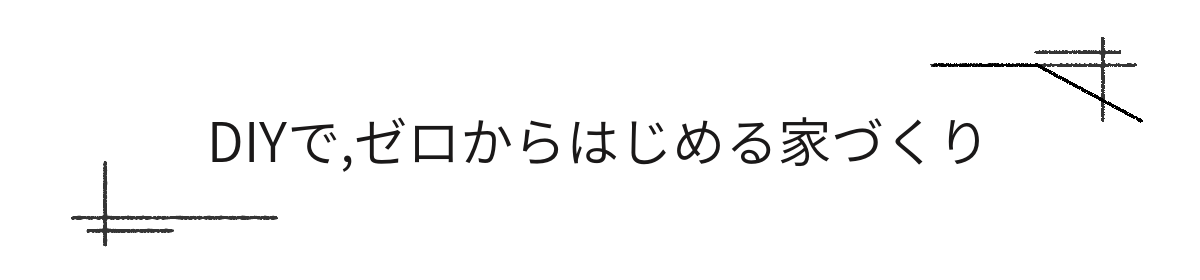

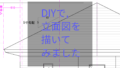

コメント